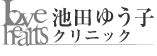妊娠出産を経験したことのある女性とそうでない女性では、乳がんの発症率に差があるということが分かっています。
乳がんの発生や進行には、エストロゲンという女性ホルモンが大きく影響します。
妊娠出産を経験しない女性はエストロゲンが分泌される期間が長くなるため、乳がんのリスクも高まるのです。
この記事では、乳がんと妊娠出産の関係性や、妊娠中に乳がんを発症した場合の治療方法について詳しく解説していきます。
出産経験と乳がん発症率の関係性とは
近年問題視される少子化の背景には、女性の社会進出が進んだことや不況による所得の低下などが大きく影響しています。
ピーク時の昭和24年に270万人だった年間の出生数は、平成28年には過去最少の98万人となりました。
また、女性が一生の間に生む子どもの推定人数を表す合計特殊出生率は、平成28年には1.44人と報告されています。
こういったデータからも、女性1人が産む子どもの数が減り、子どもを生まない女性が増えていることが分かります。
出産経験のない女性は、経産婦に比べて乳がん発症リスクが高いとされています。
この説が最初に提唱されたのは1970年代のこと。その後多くの医学者によって研究がなされ、現在では出産未経験の女性の乳がん発症リスクが経産婦よりも高まることが確実視されています。
乳がん患者の総数は、1960年代以降増え続けているのです。
1960年代には乳がんを患う人は約50人に1人であったのが、現在では約14人に1人が乳がんにかかるといわれています。
乳がん発症には女性ホルモンが影響する
女性ホルモンのエストロゲンは、乳がんの発症や進行に大きな影響を与えます。
しかし、妊娠中や授乳期にはエストロゲンの分泌が抑制されやすくなり、乳がんのリスクが減るのです。
妊娠した女性の体内ではプロゲステロンと呼ばれる女性ホルモンが優位になり、エストロゲンが体に与える影響が少なくなります。
また、産後の女性の体では母乳の分泌のために脳下垂体からプロラクチンとオキシトシンと呼ばれるホルモンが多く分泌されます。
プロラクチンには女性の体の排卵をおさえる働きがあるため、エストロゲンの量は自然と減少するのです。
出産をした回数が多い女性や授乳期間が長い女性は、エストロゲンの影響を受けにくくなり、乳がんの発症率も下がりやすくなります。
乳がんにかかっても妊娠出産は可能

妊娠中の通院により、乳がんが発見されるケースもあります。
乳がん自体がお腹の子どもに伝染したり悪影響を及ぼしたりすることはありませんが、妊娠中や授乳中に抗がん剤を服用するのは避けたほうがよいでしょう。
妊娠中であっても乳がんの治療は可能ですが、妊娠週数や乳がんの進行度合いによって対応方法は異なるので、お医者さんと治療方針をきちんと相談したいものですね。
また、「一度乳がんにかかったら妊娠出産はできない」と考える女性もいるものですが、乳がんの治療後に妊娠や出産をすることも可能なので諦める必要はありません。
妊娠中に乳がんを発症したという女性や、乳がん治療後に妊娠出産を希望している女性には、さまざまな不安があると思います。
しかし、妊娠中でも乳がんは治療できますし、乳がんにかかったことがある場合でも妊娠出産は可能です。
乳がんの疑いがある場合や乳がんについて疑問点があるときには、お医者さんにじっくりと相談しましょう。